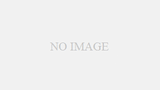「落ち着きがない」「忘れ物が多い」「お友達とトラブルになりやすい」…。子育てをする中で、我が子の気になる行動に「もしかしてADHD(注意欠如・多動症)なのかな?」と不安を感じている保護者の方もいらっしゃるかもしれません。
インターネットで検索しても、専門用語が多かったり、情報が溢れていて何から理解すれば良いのか分からなくなってしまいますよね。私の息子も夜は寝ないし、昼は一日中庭で泥遊びや走り回っているし本当に大変でした。ただしっかり特性を調べたうえで接すると考え方が変わり、いつかどこかで強みになるのではないかと今は期待しています。
この記事では、初めてADHDについて調べる親御さんに向けて、
- ADHDとは何か?基本的な知識
- ADHDの具体的な特徴や症状
- お子さんの特性に合わせた関わり方のヒント
- 「療育」というサポートについて
などを、できるだけ分かりやすく、詳しく解説していきます。
この記事が、お子さんのことを正しく理解し、親子ともに笑顔で過ごすための第一歩となれば幸いです。
1. ADHD(注意欠如・多動症)ってなんだろう?
ADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)は、日本語では「注意欠如・多動症」または「注意欠如・多動性障害」と訳されます。発達障害の一つで、生まれつきの脳機能の偏りによって、年齢や発達のレベルに不釣り合いな「不注意」「多動性」「衝動性」といった特性が現れます。
これらの特性は、多くの子供に多少なりとも見られるものですが、ADHDの場合はその程度が強く、学校や家庭など、複数の場面で生活上の困難が生じている状態を指します。
ADHDの特性の現れ方によって、大きく3つのタイプに分けられます。
| タイプ | 主な特徴 |
| 不注意優勢型 | 「うっかりミスが多い」「集中力が続かない」「忘れ物が多い」など、不注意の特性が特に目立つタイプです。女の子に比較的多く見られると言われています。 |
| 多動・衝動性優勢型 | 「じっとしていられない」「おしゃべりが止まらない」「順番が待てない」など、多動性や衝動性の特性が特に目立つタイプです。 |
| 混合型 | 不注意、多動性、衝動性の3つの特性を全て併せ持つタイプです。 |
これらの特性は、成長とともに現れ方が変化することもあります。
2. これってADHD?具体的な特徴と症状
ここでは、「不注意」「多動性」「衝動性」の3つの特性について、日常生活で見られる具体的な行動例を挙げてみます。「うちの子にも当てはまるかも」と感じるものがあるかもしれません。
⚫️ 「不注意」の具体例
- 集中力が続かない: 勉強や遊びなど、何か一つのことに集中し続けるのが苦手です。授業中に窓の外を眺めていたり、すぐに他の遊びに移ってしまったりします。
- うっかりミスが多い: 学校のテストや宿題で、分かっているはずの問題をケアレスミスで間違えてしまいます。
- 忘れ物・なくし物が多い: 教科書や水筒、宿題などを頻繁に忘れたり、おもちゃや文房具をどこかに置き忘れてなくしてしまったりします。
- 話を聞いていないように見える: 話しかけても上の空だったり、指示されたことを覚えていなかったりします。
- 片付けが苦手: 部屋や机の上が散らかっていても気にならなかったり、どこから手をつけていいか分からず、片付けを始めるのが困難です。
- 順序立てて行動するのが苦手: 朝の支度など、やるべきことを順序よくこなすのが苦手で、時間がかかってしまいます。
⚫️ 「多動性」の具体例
- じっとしていられない: 授業中や食事中など、静かに座っているべき場面でそわそわしたり、体を揺らしたり、席を立って歩き回ったりします。
- おしゃべりが止まらない: 場所や状況を考えずに、一方的に話し続けてしまうことがあります。
- 常に動き回っている: 高いところに登ったり、走り回ったりと、まるでエンジンがついているかのように活動的です。
- 静かに遊ぶのが難しい: 静かに本を読んだり、絵を描いたりする遊びが苦手です。
⚫️ 「衝動性」の具体例
- 順番を待てない: 列に並んで待つことや、ゲームの順番を守ることが苦手です。
- 質問が終わる前に答えてしまう: 人が話しているのを最後まで聞かずに、割り込んで話し始めたり、質問が終わる前に答えたりします。
- 他の人の邪魔をしてしまう: お友達の遊びや会話に、突然割り込んでしまうことがあります。
- 思ったことをすぐ口に出す: 相手がどう思うかを考えずに、思ったことをそのまま口にして、相手を傷つけてしまうことがあります。
- 危険な行動: 危ないと分かっていても、衝動的に道路に飛び出したり、高いところから飛び降りようとしたりすることがあります。
これらの行動に心当たりがあっても、すぐに「ADHDだ」と決めつける必要はありません。しかし、これらの行動が原因でお子さん自身が困っていたり、周りとの関係がうまくいかなかったりする状況が続くようであれば、専門機関への相談を検討してみてください。
他にも、逆に集中しすぎてしまう「過集中」の症状が出る方もいます。
3. 【特性別】明日からできる!関わり方のヒント
ADHDの特性を持つお子さんとの関わり方で大切なのは、叱って行動を辞めさせるのではなく、お子さんが過ごしやすくなるように環境を整え、具体的な方法を教えてあげることです。脳の特性であることを理解し、どのようにすれば問題が解決するか一緒に考えることが大切です。私も親の立場としてなかなかマインドがついていかず難しいのは経験していますが、少しずつ取り組んでいきましょう。特性に合わせた関わり方の一例をご紹介します。
✨ 関わり方の基本マインド
- できたことを具体的に褒める: 「静かにできてえらい」ではなく、「10分間座っていられたね、すごい!」のようにできた行動を具体的に褒めましょう。成功体験が自己肯定感を育みます。
- スモールステップで: 高い目標を立てるのではなく、「まずは5分だけ集中する」「持ち物を一つだけ確認する」など、達成しやすい小さな目標を設定し、少しずつレベルアップしていきましょう。
- 叱るより、やり方を教える: 脳の特性であることを理解して感情的に叱るのではなく、「次はこうしてみようか?」と具体的なやり方や代替案を一緒に考えましょう。
- 本人の気持ちを受け止める: パニックになったり、かんしゃくを起こしたりした時は、まず「嫌だったね」「悲しかったね」と気持ちに寄り添ってあげることが大切です。
🧠 「不注意」への関わり方ヒント
- 指示は「短く・具体的に・一つずつ」: 「部屋を片付けて、宿題して、お風呂に入って」ではなく、「まず、机の上にある本を本棚に戻そうか」のように、一度に伝える指示は一つに絞り、具体的に伝えます。
- 「見える化」でサポート:
- やることリスト: 朝の支度や帰宅後の流れなどを絵や文字でリスト化し、終わったらチェックを入れるようにすると、見通しが立ちやすくなります。
- タイマー: 「このタイマーが鳴るまで宿題をしよう」と時間を区切ると、集中しやすくなります。
- ラベリング: 引き出しや箱に「ぶんぼうぐ」「おもちゃ」など、写真や絵でラベルを貼ると、どこに何をしまうかが分かりやすくなります。
- 持ち物チェックを習慣に: 玄関など目につく場所に持ち物リストを貼り、前日の夜や当日の朝に一緒に指差し確認する習慣をつけましょう。
🏃♂️ 「多動性」への関わり方ヒント
- エネルギーの発散場所を用意する: 公園で思い切り走り回ったり、家の中でトランポリンで跳ねたり、体を動かす時間を意識的に作りましょう。エネルギーを発散することで、落ち着いて過ごせる時間が増えます。うちの息子はエネルギッシュ過ぎて夜眠れなかったので毎日動物園などに連れて行ってくれる放課後デイサービスを選びました。本人も毎日楽しそうで感謝しかありません。
- 事前に見通しを伝える: 「スーパーでは、10分だけお菓子コーナーを見ていいよ」「電車では、3駅だけ静かに座ろうね」など、これから起こることや守ってほしいルールを事前に具体的に伝えておくと、心の準備ができます。
- 許せる動きは認める: じっとしているのが難しい場面では、手の中で握れるボールや、いじっても音の出ないおもちゃを持たせるなど、他の人に迷惑をかけない範囲でできる動きを許容することも有効です。
🗣 「衝動性」への関わり方ヒント
- 「待つ」練習をする: 「おやつの前に10秒待ってみよう」など、ごく短い時間から「待てた!」という成功体験を積ませてあげましょう。
- 一呼吸置く合言葉を決める: 何か言いたくなったり、行動したくなったりした時に、「ストップ!」や「1・2・3」など、親子で決めた合言葉で一呼吸置く練習をします。
- 気持ちを言葉にする手伝い: お友達に手が出てしまいそうな時に、「おもちゃを取られて悲しかったんだね。貸してって言ってみようか」と、気持ちを代弁し、適切な行動を教えます。
- ルールを明確にする: 「順番を守る」「人の話は最後まで聞く」など、守るべきルールはシンプルに、分かりやすく伝えます。守れた時には、たくさん褒めてあげましょう。
4. 「療育」という心強いサポート
「療育(りょういく)」という言葉を初めて聞く方もいるかもしれません。療育とは、障害のあるお子さんや、その可能性のあるお子さん一人ひとりの発達の特性に合わせて、困難を改善・克服し、社会的に自立して生活できるように支援するプログラムのことです。
決して「障害を治す」ためのものではなく、お子さんが持っている力を最大限に伸ばし、自信を持って生きていくための土台作りと考えると良いと思います。
療育ではどんなことをするの?
療育機関によって様々なプログラムがありますが、代表的なものには以下のようなものがあります。
- ソーシャルスキルトレーニング(SST): 少人数のグループで、ゲームやロールプレイング(役割演技)などを通して、対人関係や社会のルールを楽しく学びます。
- ペアレント・トレーニング: 保護者が子供の行動への理解を深め、適切な褒め方や指示の出し方など、具体的な関わり方のスキルを学びます。親のストレス軽減にも繋がります。
- 応用行動分析(ABA): 人の行動を分析し、良い行動が増えるように、適切な行動の直後に褒めるなどのアプローチで働きかけます。
- 作業療法(OT): 手先の不器用さや感覚の過敏さ・鈍感さなどに対して、遊びを通して体の使い方や感覚の調整を促します。
- 言語療法(ST): コミュニケーションや言葉の発達に関する支援を行います。
どこに相談すればいいの?
もしお子さんの発達について心配なことがあれば、一人で抱え込まず、以下の窓口に相談してみてください。
- かかりつけの小児科
- 地域の保健センター、子育て支援センター
- 児童発達支援センター
- 発達障害者支援センター
これらの場所で相談することで、専門の医療機関や療育機関を紹介してもらえたり、必要な情報を提供してもらえたりします。
最後に:保護者の方へ –
ADHDの特性を持つお子さんの子育ては、時に大変だと感じることがあるかもしれません。周りの子と同じようにできないことに焦ったり、どうして言うことを聞いてくれないのかと思うこともあるかもしれません。
うちの息子も常に目が離せず、一日中走り回れるタイプで夜も眠らず本当に大変でした。ただある意味その尖った特性は、見方を変えれば長所にもなりえると思うようにしてからは、心が落ち着いた覚えがあります。
正月に私のダイエットも兼ねて息子と2人で2時間耐久の鬼ごっこをしましたが、当然全く歯が立たず、息子の好きなことは飽きずにずっとやり続ける能力は才能だと改めて思った記憶があります。
特徴を長所に!特徴別向いてる仕事
- 衝動性 → 即行動に移せるスピード感があり、チャレンジ精神が旺盛
- すぐに行動できるフットワークの軽さはチームにスピード感をもたらせる存在。起業家や営業職など現場で即断即決が求められる仕事で能力を発揮できるかもしれません。
- 多動性 → 好奇心旺盛でエネルギッシュ
- 常に動いていることが苦ではなく、パワフルな存在として周囲を元気づける存在。イベント設営や飲食業などの次々にやることが発生する仕事や起業家や自営業など自分でルールを決めて動き回れる環境で力を発揮できるかもしれません。
- 感情のコントロールが苦手 → 感性が豊かで共感力がある
- 繊細な感性は、作家や小説家など心を動かす作品を生み出す力になります。
- 高い共感力は他人の気持ちに気づきやすく、相手が安心できる存在になれます。相談員やカウンセラー、アニマルトレーナーなどの仕事で力を発揮するかも知れません。
- 過集中 → 興味のあることに没頭できる
- 好きなことに対しての集中力は、他の人の何倍もの成果を生み出せます。プログラマーや研究者など特定の分野で大きな成果を出せる可能性があります。
今現在、放課後デイサービスや児童発達支援増えてきており様々な特徴があります。
当サイト「虹マッチ」では各施設のそれぞれの特徴やコラムにて発達に悩みを持つ方々に向けてけ情報発信をしています。私自身も悩みに悩んで失敗や成功を経験してきました。是非ご利用いただければ幸いです。
これからも子育て頑張っていきましょう!